内定から1年経ちました。前回の投稿からもほぼ1年経ちました。この1年で多分他の人の8ヶ月分くらいは進歩した気がします。というのも1月の勉強時間が元日の5時間のみという嘘のような怠惰さで2Aの単位を殆ど落としたからです。終わってますね。留年ピンチかもです。3Sは多少勉強したので、一応各科目語ろうかな。
必修科目(講義)
・電磁気学Ⅱ
まず電磁場の運動量とか応力テンソルをやって、そのあと物質中の電磁場、電磁波の屈折とかをやりました。伝送線とかいうテーマも最後の方に出てきて意味不明でしたが試験には出ませんでした。
7月のある日にマクスウェル方程式を何も見ないで書けるようになりました。こういう瞬間は突然くるものですね。中間試験を教員が予告してたのに当日やっぱりやりませんというので何人かがブチギレてました。
・量子力学Ⅱ
2Aの量子力学Ⅰを何もせずに落としたので、演算子の固有値が物理量になることを初回の講義で知りました。4月と5月で清水量子論を読んで、6月と7月は図書館でいろいろかいつまんで角運動量の合成とか摂動論とか勉強しました。小学生の頃から、量子力学という学問があってそこでは物事が確率で決まる、みたいな話は知ってたので、それが解き明かされていくのは結構楽しかった。でもスピンと磁場の相互作用のところはよくわからなかったのでAセメまた。
・統計力学
なんか、物理学科にくるような人ってだいたいは宇宙!!素粒子!!みたいに憧れてくると思うんです。自分もそうです。でも結局大多数は物性に行きます。そのきっかけがこの科目なのかなあという気がします。身近な物質の性質を説明できて面白い分野だなと思いました。それでもなお宇宙や素粒子への憧れが勝る、という意思の強い者が素核・宇宙方面に行くんだなあと思います。
・流体力学・地球流体力学
理物開講の流体力学は世紀末を疑うほど楽単です。1時間ほどで終わる中間・期末レポートを出して終了。期末レポートの最後には「新たな装置を考案せよ」という課題がありましたが、気力がなかったのでそこは空欄にしましたが、良がきました。
地球流体はいかにもな流体力学の地物開講の講義。出席をとられますが月曜1限だったので最初と最後しか行けませんでしたが、図書館で流体力学の良さげな本を探して3日くらい勉強して乗り切りました。期末は過去問のほぼ使い回しなのがありがたかったです。
物理学演習Ⅲ・Ⅳ
Ⅲは偶数クラスで、教員がコミュ強だったので雰囲気良さげでした。やはり早めに発表するに限りますね。試験は3分の1くらいしか解けませんでしたが、その場レポートを後日慌てて全部提出した甲斐あって良が来ました。
ⅣはS2A1という謎の開講区分なので、 11月にある期末をがんばります。発表はもう済ませました。中間は大問3つ中最初しか解けなかったので、また期末後にその場レポートをまとめて出すことになりそうです。
物理学実験I
chatgptのおかげでレポートのtex打ちや解析はだいぶ楽でした。生成AIない時代にtexとかプログラミング身に付けてた人は本当にすごいと思います。実験を通じて物理力はそんなに上がった気がしませんが、レポート作成がPCの操作とかtexの能力向上に結構役立った気がします。でも全体的にもうちょっとレポートのクオリティ高く仕上げたかった。
計算機実験
レポート一度も出さずに落としました。
6月は気力が尽きてたんですが、3つあるレポートのうち2つの締め切りが6月にあったので、2つ目を出せなかった時点でもうダメだろうなと思って3つめも放棄。
終わりに
3S頑張ったと言っても6月は実験以外授業も行ってませんでした。実験は1つでも休むと即留年なのでなんとか行って、実験レポートも超低クオリティーながら出してました。2Sでサークルのことで盛大に病んで以降、普通に動ける時期となんもできない時期が繰り返しやってくるんですが、それが試験期間に被ると2Aのようになります。被らないと3Sのように落単1つ程度の傷で済みます。
3Aは必修のゼミがあります。なんか経路積分?の英語の文献を輪読するらしいです。メンバーの中で自分が下に突き抜けていることは確定なので、置いてかれて病む→勉強できない→もっと置いてかれる→もっと病む・・・・みたいな悪循環にならないことを祈ります。

-120x68.jpg)
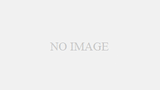
コメント